日本の結納における伝統的な「結納用品一式」についてご説明いたします。

結納(ゆいのう)は、日本の伝統的な婚約儀礼で、両家の縁組みを正式に認め合う重要な儀式です。この歴史は平安時代まで遡り、当初は単に持参金や贈り物の交換でしたが、時代と共に儀式化され、象徴的な意味を持つ品々が定められていきました。

基本的な結納用品一式
1. 結納金(ゆいのうきん)
- 最も重要な品で、現金を水引で飾った特別な包みに入れます
- 「寿」や「鶴」などの吉祥文字を記した紙に包まれることが一般的
2. 結納品(ゆいのうひん)
- 九品目(ここのしなもく)が一般的で、それぞれが幸福な結婚生活を願う象徴的な意味を持ちます
- 末広(すえひろ):「末広がり」という言葉のように、将来の発展を願う扇
- 熨斗鮑(のしあわび):長寿と繁栄の象徴
- 昆布(こんぶ):「子宝」を願う意味の「子生ぶ」に通じる
- 干しするめ(かんするめ):夫婦の堅い絆を表す
- 長熨斗(ながのし):長い人生の幸せを願う
- 白羽二重(しろはぶたえ):純潔の象徴
- 懐剣(かいけん):花嫁の貞節を表す
- 扇子(せんす):広がる幸せと家の繁栄
- 真田紐(さなだひも):夫婦の絆を象徴
3. 目録(もくろく)
- 贈る品物を記した正式な書面
- 結納品の内容と意味を記載
- 美しい和紙に毛筆で記されることが多い
地域差と変遷
結納用品は地域によって「関東式」「関西式」など内容や形式に違いがあります。近年では簡略化された「略式結納」や「結納返し」など現代的なアレンジも見られます。
現代における結納
結婚式のスタイルが多様化する中、結納を省略したり、より簡素化した形で行うカップルも増えています。しかし、日本の伝統文化として、また両家の正式な顔合わせの場として、その意義は今なお重要視されています。
結納は本来、使いの方(使者)が結納品を持って両家を行き来する行事でした。
両家がホテルなどで直接会って結納品を交換するのは略式になります。
投稿者プロフィール

- 日本婚礼写真協会、ホームページ編集部です。
最新の投稿
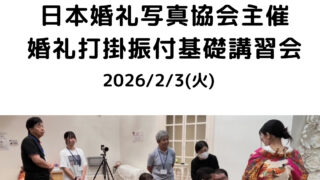 ブログ2026年1月14日ASUKABOOKは、2月3日(火)に神奈川県川崎市高津区にて開催される
ブログ2026年1月14日ASUKABOOKは、2月3日(火)に神奈川県川崎市高津区にて開催される ブログ2026年1月14日Photo Nextの講習会を振り返って
ブログ2026年1月14日Photo Nextの講習会を振り返って ブログ2026年1月7日PHOTONEXT 2026 全国各地より多数の皆様にご参加を賜りました。
ブログ2026年1月7日PHOTONEXT 2026 全国各地より多数の皆様にご参加を賜りました。 ブログ2026年1月3日PHOTONEXT 2025 婚礼和装振付セミナー
ブログ2026年1月3日PHOTONEXT 2025 婚礼和装振付セミナー

