婚礼和装の振付の成り立ちと歴史

婚礼和装の振付とは、和装の新郎新婦が写真撮影や式典で美しく見えるように、立ち姿や動作を整える所作のことを指します。この振付には、日本の伝統的な礼法や美意識が反映されており、時代とともに発展してきました。
1. 平安時代:婚礼儀式の始まりと装い 平安時代の貴族社会では、「結婚式」という明確な儀式はなく、「妻問い婚(つまどいこん)」と呼ばれる形が一般的でした。 • 振付の原型:この時代の女性は十二単(じゅうにひとえ)をまとい、立ち居振る舞いは極めて優雅であることが求められました。袖を美しく動かす、静かに歩くといった所作が婚礼の場でも重視されていました。
2. 室町・戦国時代:武家社会の婚礼儀式 武家社会では、婚礼が家同士の結びつきを強める重要な儀式となり、より格式が高まりました。 • 和装の発展:この時代には、白無垢(しろむく)の原型となる装束が登場し、儀式の場での立ち居振る舞いがより重視されました。 • 振付の要素:新婦は「三つ指をつく」動作や、ゆったりとした歩き方を身につけるようになり、所作に気品が求められるようになりました。

3. 江戸時代:武家婚礼の形式化と和装の定着 江戸時代に入ると、婚礼の儀式がより明確に整えられ、「婚礼衣装の振付」も確立されていきました。 • 白無垢と色打掛の確立:白無垢は武家の正式な婚礼衣装となり、色打掛(いろうちかけ)も華やかな装いとして一般化しました。 • 婚礼作法の発展:この時代には「婚礼振付師」に相当する人物が現れ、新郎新婦が美しく見える立ち方や動作が指導されるようになりました。例えば、裾を乱さずに歩く「内股歩き」や、襟元を正しく整える動作などが意識されるようになりました。
4. 明治・大正時代:西洋文化の影響と伝統の融合 明治時代になると、西洋文化の影響で洋装の婚礼も普及しましたが、和装婚礼の伝統も残り続けました。 • 写真撮影の登場:写真技術の発展により、婚礼写真が一般的になり、新郎新婦が美しく見える振付が重要視されるようになりました。 • 動きの美しさを重視:この時期、和装の立ち姿や座り姿だけでなく、歩き方や袖の扱い方など、写真映えするポージングの振付が発展しました。
5. 昭和・平成・令和時代:現代の婚礼和装振付 昭和から平成にかけて、ウェディングドレスの人気が高まりましたが、和装婚礼の需要も根強く残りました。 • 現代の婚礼和装振付の特徴 1. 伝統的な美しさの継承:白無垢や色打掛を着用した際の優雅な立ち姿、裾の扱い方、指先の揃え方などが重要視される。 2. 写真映えを意識したポーズ:正面だけでなく、斜め向きの姿勢や袖の広がりを活かしたポージングが指導される。 3. 動画やSNS対応の振付:和装での所作を動画で残すケースが増え、より自然で美しい動きが求められる。
6. まとめ 婚礼和装の振付は、日本の伝統文化の中で長い歴史を経て発展してきました。平安時代の宮廷文化に端を発し、江戸時代に武家の格式として確立され、明治以降の写真文化の影響で現代のスタイルへと進化しました。 現在では、伝統的な所作を守りながらも、写真映えや動画撮影を意識した新しい振付が取り入れられ、より美しく洗練された和装婚礼の演出が行われています。
理事 松井一元
投稿者プロフィール

- 日本婚礼写真協会、ホームページ編集部です。
最新の投稿
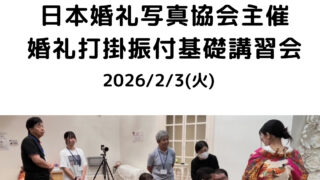 ブログ2026年1月14日ASUKABOOKは、2月3日(火)に神奈川県川崎市高津区にて開催される
ブログ2026年1月14日ASUKABOOKは、2月3日(火)に神奈川県川崎市高津区にて開催される ブログ2026年1月14日Photo Nextの講習会を振り返って
ブログ2026年1月14日Photo Nextの講習会を振り返って ブログ2026年1月7日PHOTONEXT 2026 全国各地より多数の皆様にご参加を賜りました。
ブログ2026年1月7日PHOTONEXT 2026 全国各地より多数の皆様にご参加を賜りました。 ブログ2026年1月3日PHOTONEXT 2025 婚礼和装振付セミナー
ブログ2026年1月3日PHOTONEXT 2025 婚礼和装振付セミナー

