色打掛の成り立ち


色打掛(いろうちかけ)は、日本の伝統的な婚礼衣装の一つで、特に新婦が挙式や披露宴で着用する華やかな着物です。 その成り立ちや歴史について簡単に説明します。 色打掛は、元々は平安時代から使われていた「打掛」(うちかけ)が起源とされています。 打掛は、上着の一種で、室内での生活に合わせて、普段着としても着用されていました。 時代が進むにつれて、特に江戸時代に入ると、結婚式やお祝い事の際に特別な装いとしての役割が強まりました。 色打掛が「色」と名付けられているのは、様々な色合いや模様が施されているためです。 色打掛は特に華やかさを重視しており、絢爛豪華な刺繍や染めが特徴です。 また、通常の打掛とは違い、色打掛は表地に多彩な色やパターンを施し、衣装全体が華やかに演出されるようになっています。 色打掛は、婚礼における重要なシンボルであり、新婦の美しさや家族の繁栄を表現する意味合いも持っています。 色打掛を着ることで、新婦は伝統や文化を尊重しつつ特別な日を祝うことができるのです。 最近では、伝統的な色打掛に加え、現代的なデザインやカラーバリエーションも増え、新婦が自分の好みを表現できる機会も広がっています。 和装の歴史を知る事も、お客様からの信頼を得る1つの要素になります。
理事 松井一元
投稿者プロフィール

- 日本婚礼写真協会、ホームページ編集部です。
最新の投稿
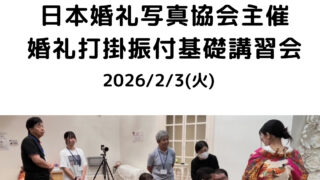 ブログ2026年1月14日ASUKABOOKは、2月3日(火)に神奈川県川崎市高津区にて開催される
ブログ2026年1月14日ASUKABOOKは、2月3日(火)に神奈川県川崎市高津区にて開催される ブログ2026年1月14日Photo Nextの講習会を振り返って
ブログ2026年1月14日Photo Nextの講習会を振り返って ブログ2026年1月7日PHOTONEXT 2026 全国各地より多数の皆様にご参加を賜りました。
ブログ2026年1月7日PHOTONEXT 2026 全国各地より多数の皆様にご参加を賜りました。 ブログ2026年1月3日PHOTONEXT 2025 婚礼和装振付セミナー
ブログ2026年1月3日PHOTONEXT 2025 婚礼和装振付セミナー

